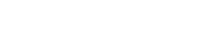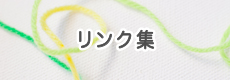綴られた言葉集
看取り、介護、死に関して綴られた言葉を抜粋、引用してお届けするページの第二段目の本棚です。ただし引用した文章はあくまでも管理者が個人的に選択した部分です。綴られている本のタイトル、著者、発刊年、出版社と本の値段がわかるようになっていますので、ご興味を持たれた方は、本そのものを入手され、ご自身の「綴られた言葉集」を編集してみてください。
『驚きの介護民俗学』
「介護予防という言葉には、介護は予防されるべきもの、という考え方が露骨に反映されている。つまり、要介護状態になることは否定的にとらえられているのである。もちろん元気に長生きできたらそれに越したことはないかもしれない。しかし言うまでもなく、誰しも年をとる。であれば誰もが要介護状態になりうるのである。介護される側になるというのは決して特殊で特別なことではなく、人間にとっては誰しもが迎える普遍的なことであり、自分もそうなるのだ。そういった想像力が、介護を問題化するのではなく、介護を引き受けていく社会へと日本社会を成熟させていくための必要条件だと思える。」pp227-223
「文化人類学から見た生と死」
「死が、いずれは再び生まれ出るための準備をする「あの世」への「この世」からの旅立ちであると信じるなら、死は人生の終末ではなく区切り目であり節である。人の「一生(ひとつの生)」の間にできることはわずかでありいつか再生して次の世で引き継ぐことができるなら、どのような人生も決定的な敗北や失敗にはならない。こうした人生観は人々を死の絶望や虚無感から救ってきたことが伝統的社会に生きてきた人々の語りから明らかになってくる。」pp266-267
『在宅で死ぬということ』
「病院で最期を迎える際には、ほとんどの患者さんに、心臓の動きを見るモニターがつけられていました。どちらかといえば、患者のそばにいるのは、いろいろな処置をするための、私たち医療者のほうだったと思います。
家族がすぐそばに行くときは患者さんが亡くなったときで、それまでは、私たち医療者の一歩外側で、涙を流しながら呆然と見守っているか、緊急の場合は、病室の外で不安げに待機していることもあります。
いまは、まるで逆です。モニター装置もなにもなく、点滴など薬もまったく使用せずに、黙ってなすすべもなく概観しているのは、医療者としてなんとつらいことだろうと、私は感じていました。
しかしその反面、これが人間の本来の死に方なのではないか。これこそが、本当の在宅のよさなのではないかと緊張しながら初めての在宅死のすばらしさにいいようのない感動をおぼえていました。」pp33-34
「在宅で安心して死ねる日がやってくる」
「病院は病気を治す場所だが、自宅は死が避けられない人が最期まで希望を持って生活できるように支える場所である。」p141
「家にはハードとしてのハウスと、家族としてのホームがあるが、在宅というのは特にソフト面が満たされることであり、家族が一緒なら必ずしも自宅である必要はない。」p146
「在宅を選んだのは死を受容したからではなく、死ぬまで生きていることを実感したかったからだと思う。野生動物と同じで、人間も自由で安らぎに満ちた死に場所がいい。住み慣れた自宅は、最期まで生を全うできる場所でもあるのだ。」p152
「在宅ケアと情報-在宅ホスピスケアを実現するために」
「家で人生の最期のときを過ごす人々にとっての健康とは何なのでしょうか。それは、たとえ病気は治らなくても、今日を生きる意味を見出し、自分らしく死ぬまで行ききることではないでしょうか。」p146
「日本の医療は伝統的に医師を頂点としたパターナリズムで医師の指示・管理の下に医療サービスが提供されてきました。しかし生活という視点が加わった在宅ケアでは、医師のみの力量で十分なケアはできません。多くの専門家が知識や技術そしてケアの考え方を出し合い、利用者や家族の意向をくんでサービスを提供することが必要となってきたのです。」p153
「死までの過程を十分に説明しておけば、最期の看取りは家族だけでこころゆくまで看取られます。死の周辺でおきる長く人生を共にした家族だからわかることを死にゆく人と家族が共有でき、人生の総決算をする大切な時だと考えます。」p174
『死を見つめる心 ガンと戦った十年間』
「少し古い一冊ですが、図書館でみつけました。筆者は東大教授の高名な宗教学者です。がんとの闘病中に綴られた死を見つめる思索の数々です。
「死の事実は、古往今来、普遍である。しかし、死の事実が普遍であるということは、死を見る人間の目にも変わりがないということではない。人間の、死という事実の把握の仕方、死に対する態度には時代が進むにつれて、徐々の、しかし、顕著な変化が現れて来ている。死の事実は普遍であるけれども死の意味は変わってきた。」p116
「人間にとっての死の苦しみというのは、裏返していえば、生命への執着である。生命を絶たれようとするものにとっての、満たされざる生命欲の猛烈な抵抗に発する苦しみである。生命の餓えである。」p124
『大・大往生』
「死を受け入れる前にしなければいけないことがある。年をとることを受容することだ。死は必ずやってくる。それは生き物の大原則である。たとえ、自分ががんや脳卒中で倒れても、まずは病気そのものを知ることが大事。なぜならば、自分の人生をまっとうするための選択は、病気のことを知っていなければ、自己決定できないからだ。」pp166-167
「どんな状態になっても、昨日よりちょっと良くなっただけで、うれしくなる。もうやれることはないなんてことはないのだ。生きている限りやれることはある。」p201
『いのちの砂時計-終末期医療のいま』
「家出患者さんが息を引き取る場面に立ち会うと、ご家族が抱きしめたり身体をさすったり、その光景は静かで優しい。亡くなった後も家族に悲愴感がなく、「最期まで頑張ったね」と泣き笑いで言える良さがある。・・死はみんな違って定型がない。」p114
『死にゆく患者の心に聴く 末期医療と人間理解』
「その人の生きてきた過程が死に至る過程に凝縮して現れる。生きてきたように死んでいく人たちをみていると、しっかりと生きねばと思う。家族に恵まれる人と、恵まれない人の最期の差をみると家族を大切にする必要を教えられる。」p230
『子どもと老人の民俗誌』
「いま、死はかつてのように日常生活の延長線上にはなく、病院の医療施設のなかに閉じ込められ、とくにこどもから死は遠ざけられている。・・中略・・現実の死とであったことがないこどもたちには、死がやりなおしのできるものであるように錯覚させてしまう。死の意味が非常に希薄になってきているのである。」pp133-134
「死を直視する機会が減ったということは、結局は生ときちんとむきあう機会も減ったということでもある。老人たちはイエやムラにおいて経験や知識の宝庫として尊敬されるだけではなく、その存在そのものが、生きることと死ぬことの意味を、世代を超えて考えさせるという役割をはたしていたのである。」p134
『死者の花嫁 葬送と追想の列島史』
筆者は東北大学大学院の教授で、「死」を残された研究者人生における最重要の研究テーマとしている学者です。一遍の詩を読むような語りに深く魅せられました。
「一つの死を見送ることは、その人の人生が何であったかを問うことなのです。
それはとりもなおさず、自らの人生の意味を問う行為にほかならない。人は他人の死を見つめることによって、生きることの意味を自問する。そうした営為を通じて、人は個人の生を背負い、残された日々をその人と生きていくことを決意するのである。」p196-197